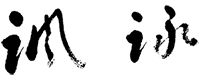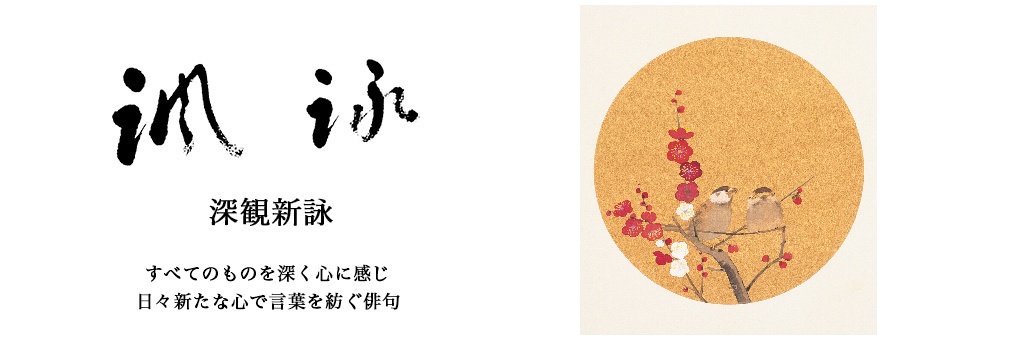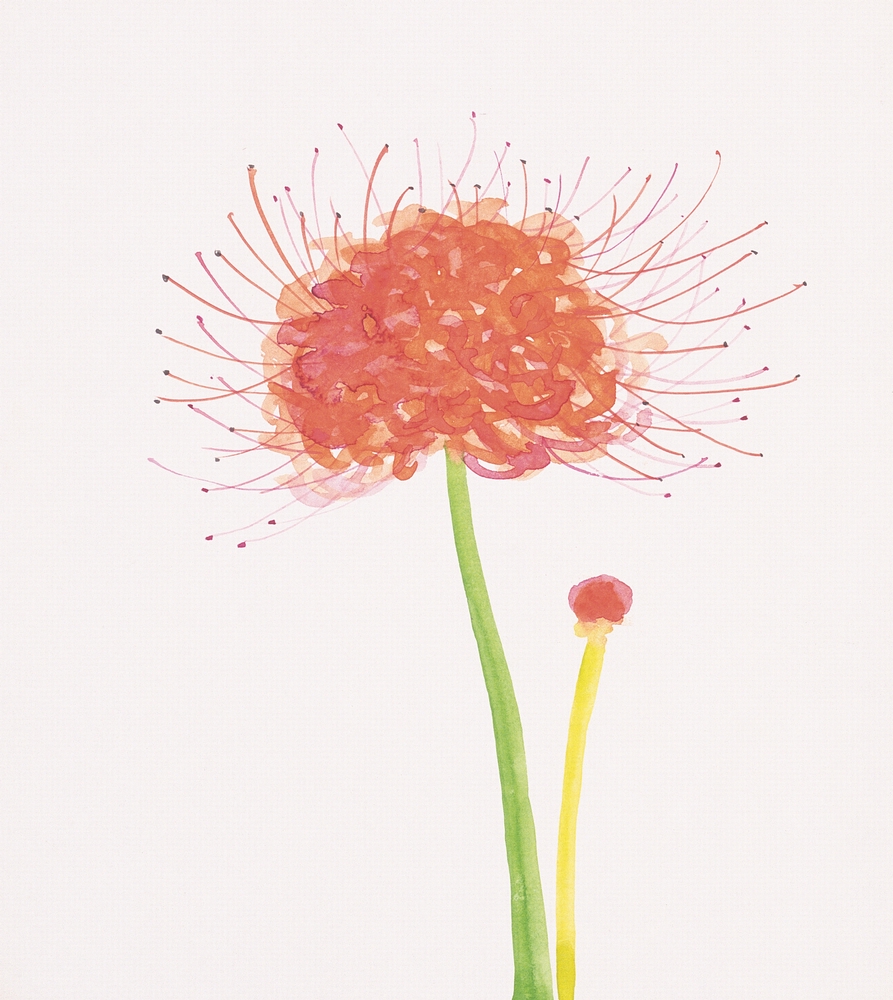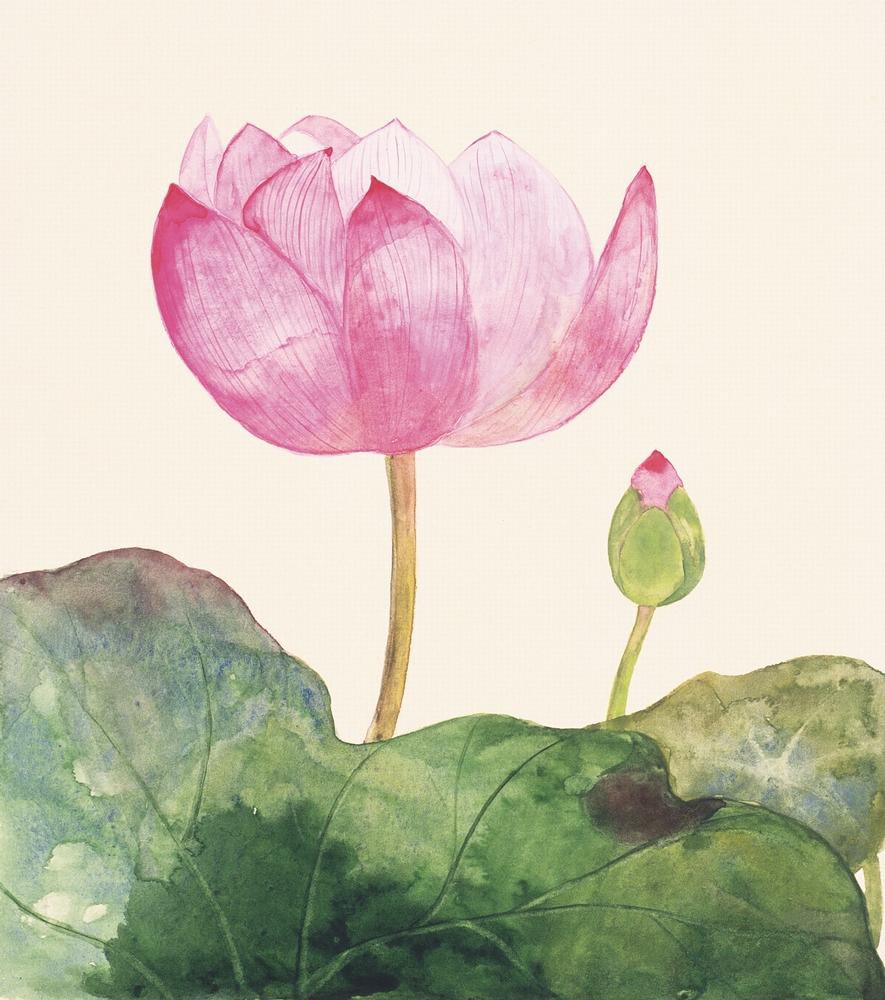華凜主宰の俳句
初冬の街
初冬やガラスケースの中の街
木犀の風の余韻といふほどに
茶の花や塗の小皿に金平糖
襟元は柿茶の小菊着て利休
幸せに理由はいらぬ日向ぼこ
追憶は夕暮れの色返り花
蓮枯れて浮世の重さ失ひぬ
冬の虫いのちたのしめたのしめと
鳰潜る真昼の白き月の下

雑詠 巻頭句
満月を上げて茶畑碧光り
木下紀子
句評 八女の茶畑が一面に広がる上に大きな満月があり、煌煌と照らして
いるようす。「碧」とは深くあおい色。まるで絵本の一場面のような光景。
華凜
雑詠 次巻頭句
長からぬ人生にして夜は長し
森本昭代
句評 人の人生は決して長いとは言えない。それでも秋の夜長の寂しさは、
作者には長すぎるように感じた。亡き夫を想う心が句から伝わる。 華凜
誌上句会 特選句
有本美砂子選
号外の手もとに望の月明り
奥田美恵子
岩田雪枝選
祇王寺の苔に降りたる冬紅葉
水口康子
下田育子選
移民坂くだれば月の神戸港
新谷須磨子
古山丈司選
どの色もゆづり合ふ色草紅葉
今井勝子