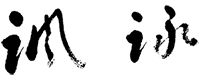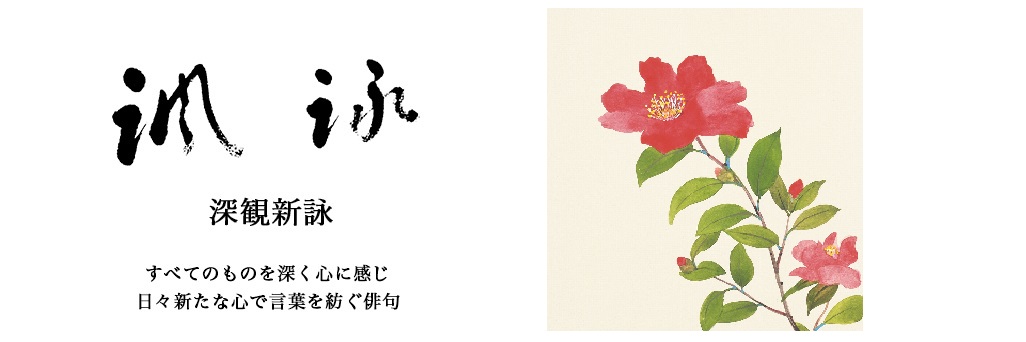華凜主宰の俳句
君眠る
読初の古事記大蛇のところより
大枯野かつて天動説の空
鰭酒の夜を灯して港町
山茶花や恋とも言へぬ恋をして
令和六年十二月二十日、弟高広五十四歳にて逝く。
君眠る六甲の山眠るとき
こんなにも美しき冬日に迎へられ
時雨虹母より先に泣くまいぞ
さみしさに己が肩抱く冬至風呂
やうやくに涙あふれて年の逝く

雑詠 巻頭句
影ありて大綿に白現れる
石田陽彦
句評 ゲーテの言葉「光あるところに影あり」は真理だと思う。
この句にはその逆の真理を感じた。大綿の白は光。しっかりとした
写生の目が、この世を照らす小さな光を捉えた。 華凜
雑詠 次巻頭句
帰り咲く左近の桜神さびて
森本昭代
句評 春に咲く桜が、冬のあたたかな日差しに帰り咲いている様子は
神の御業のよう。御所内裏の庭の「左近の桜」なら殊更、神々しく輝く。
下五の「神さびて」が見事。 華凜
誌上句会 特選句
和田華凜主宰選
冬ぬくし姫街道に目安箱
柴田のり子
中谷まもる副主宰選
嚔して俊太郎の詩諳んじる
石川かずこ
金田志津枝選
大根抜き畑の底を覗き見る
下田育子
柳生清秀選
YESかNOか神農の虎の首
奥田美恵子