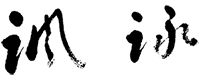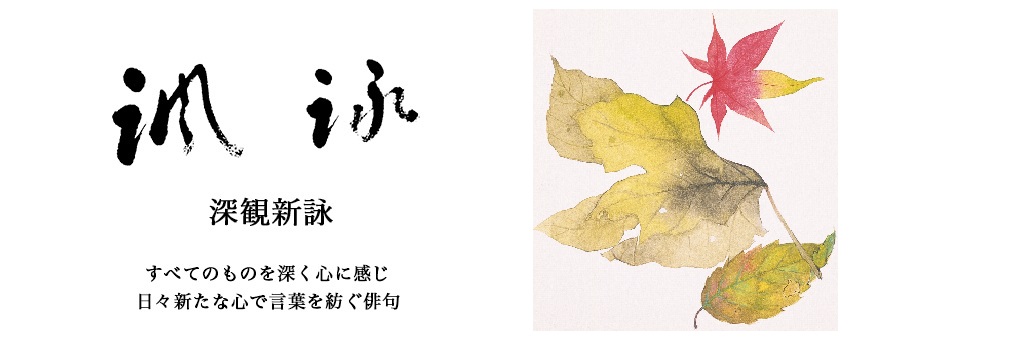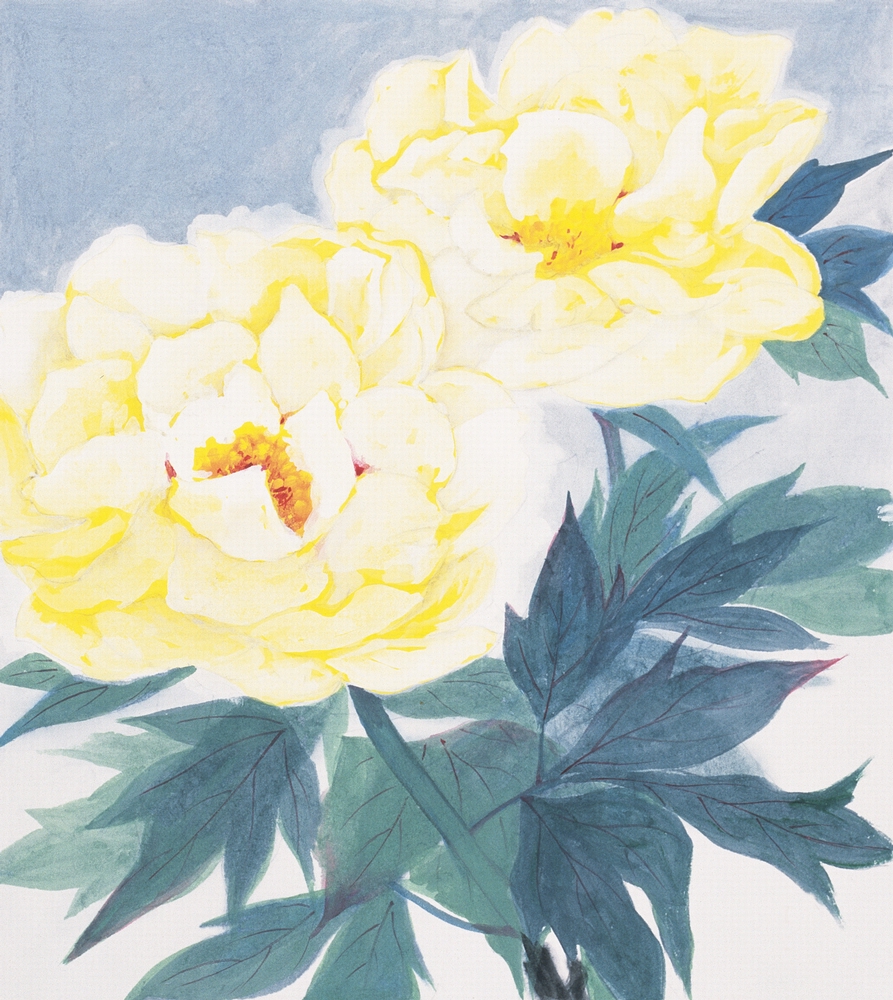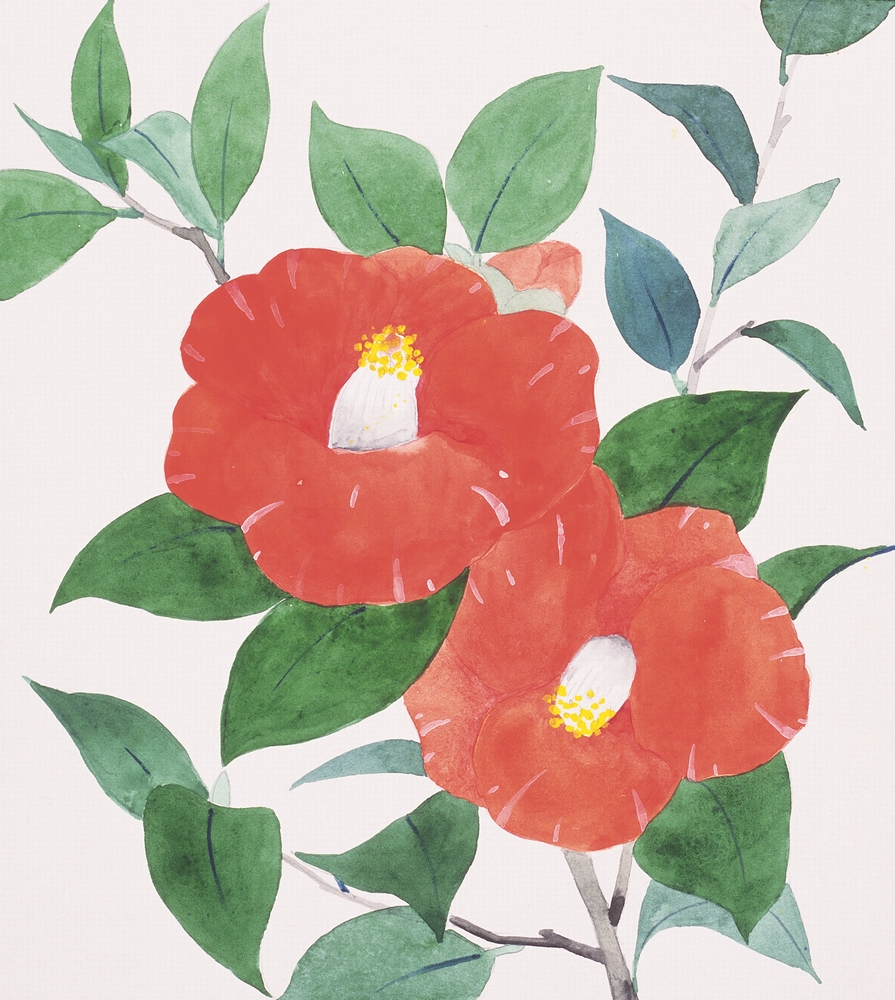華凜主宰の俳句
たいくつさうな指
香水はミツコ人には物語
夏帯の花鳥六区に仲見世に
厨よりきれいな声す夏暖簾
風鈴を揺らしたいくつさうな指
紫陽花の藍を尽して奥吉野
畳むには惜しき花ある扇子かな
閉館の絵画展より夕日傘
銅像の目の黙深し五月闇
航路いま赤道直下夏の月

雑詠 巻頭句
新緑の夜を戻りて身の湿り
今井勝子
句評 下五の「身の湿り」が見事。読み下した瞬間に筆者の身に
湿度が伝わった。新緑の命のざわめく夜を作者自身に宿している。
艶の句。 華凜
雑詠 次巻頭句
敦盛の修羅を舞ふべく更衣
青山夏実
句評 能楽師の「更衣」を詠んだ句であろう。武人がシテになる能を
修羅物と言い、修羅道に落ち苦しむ様が描かれる。「平家物語」に
多くある。「敦盛」は殊によい。 華凜
誌上句会 特選句
和田華凜主宰選
万緑を逆さに湖の深さかな
森本昭代
中谷まもる副主宰選
父の忌の太田胃散の上の蟻
古山丈司
金田志津枝選
古墳秘め風土記の丘の緑美し
太田倫子
柳生清秀選
流行を少し取り入れ更衣
多田久子