柳生清秀
畿内の春
耕の無駄なく動く老の鍬
八荒に魁荒るる浪速場所
遅咲の水仙こその秘むるもの
今泣いた子も楤の芽も笑む陽気
貝寄風の吹く住易き街なりし
葱坊主裏より入る飛鳥寺
蛍烏賊光尽して果てにけり

有本玲子
バックハグ
若夏や言の葉美し万座毛
島遥かテラスの朝餉石蓴汁
空に揺れ海に揺れゐて茅花の穂
沖縄の旅二期作の田植中
紅型に火の色燃えて仏桑花
バックハグして夕焼の水平線
くちなしの花枕辺に旅果つる
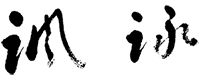
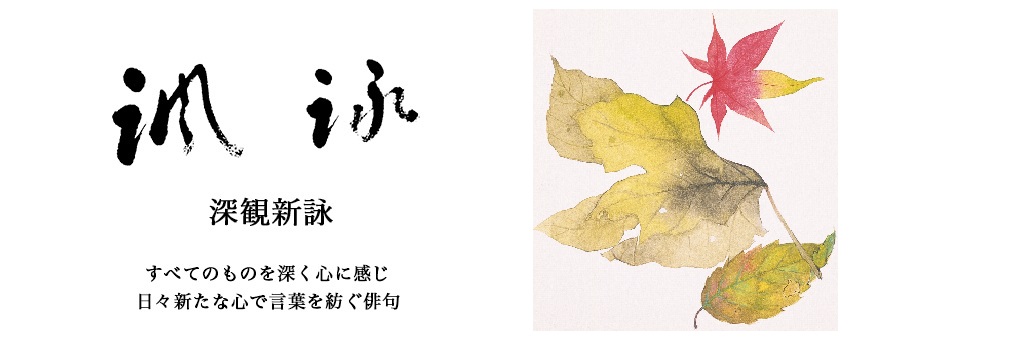
耕の無駄なく動く老の鍬
八荒に魁荒るる浪速場所
遅咲の水仙こその秘むるもの
今泣いた子も楤の芽も笑む陽気
貝寄風の吹く住易き街なりし
葱坊主裏より入る飛鳥寺
蛍烏賊光尽して果てにけり

若夏や言の葉美し万座毛
島遥かテラスの朝餉石蓴汁
空に揺れ海に揺れゐて茅花の穂
沖縄の旅二期作の田植中
紅型に火の色燃えて仏桑花
バックハグして夕焼の水平線
くちなしの花枕辺に旅果つる
牛蛙声ふるはせて北信濃
どの部屋も花の名つけて宿涼し
夏霧の晴れて絵本のやうな村
どこまでも夏野の続く野沢村
雲の峰戸隠山も妙高も
もろこしも玉子も茹でて麻釜の湯
汗かいて外湯めぐりも野沢村
人涼しあつ湯ぬる湯と教へくれ
外湯には小さき神棚髪洗ふ
大湯出てぶだうジュースと端居して
端居して真向ひに見ゆ道祖神
外湯出て祭提灯ともる頃
路地沿ひにたけのこ祭屋台の灯
たけのこ飯信濃の人のやさしかり
千曲川音頭聞こゆる祭かな
鯖󠄀缶も入れてたけのこ汁うまし
飯山に仏壇通り濃紫陽花
笹ずしの笹の葉ほのと北信濃
四十年ぶりに逢ふ人夏薊
水尾てふ涼しき地酒酌みかはす

三月十九日、立子賞を祝う会小石川後楽園
忘るまじけふ初花に会へしこと
春瀧の音に洗はれゆく心
鳥声のいくつ重なる春野かな
祝ぐ心偲ぶ心も花の雨
みな染る桜に触れて来し風に
けふの命けふを満たして花万朶
べつかふ飴薄暮透せて夕桜
この辻に夜叉となるやも花月夜
たましひの身を離れゆく花衣

生まるるも逝くのも一度二月尽
小林一鳥
句評 「二月尽」に注目。花鳥諷詠を提唱した虚子の誕生日は二月
二十二日。作者も同じ誕生日らしい。昨年二月二十七日に汀子先生は
帰天された。一度きりの生を深く思う月。 華凜
焼きし野のやがて寂しき風渡る
古山丈司
句評 ふと芭蕉の〈おもしろうてやがて悲しき鵜舟かな〉を思った。
芭蕉の句は心の写生であるがこの句は野焼の風景を見事に写生された。
「寂しき風渡る」にある余情に感服。 華凜
梅咲くや宝梅てふはよき住所
小林一鳥
毛のなかの羊とり出すやうに刈る
野村国世
初雪はをさなでゆきし子の匂ひ
石川かずこ
絵馬の裏まで書く受験志望校
福田三千男
「ビヤホール見たい」と書きし子規のこと
あぢさゐの青の途中の阿弥陀仏
百里来て伊予に聞き留むほととぎす
砥部焼の青の涼しきとんぼの絵
百を越す簾ぐるりと坊ちやん湯

師を祝ぐと外壕通ゆく薄暑
街薄暑若さは歩巾より溢れ
野草踏み行きて薄暑の香の立ちぬ
靴濡らし沢渡りゆく薄暑かな
君と会ひ別れし小石川薄暑
春待つや臨月の娘は髪切つて
梅早し日矢射すところ兆あり
令和五年二月七日 初孫誕生
産声に開きて今朝の梅真白
素数の日選りて二月に生れたる
新生児指まだ解かず蕗の薹
命名の墨黒黒と梅真白
草萌えてふくふくしたる埴輪かな
おはじきもおじやみも卓に雛の間
雛飾り嫁して娘のをらぬ家

滝凍る月に青さを貰ひつつ
今城 仂
句評 鋭い感性の写生句。その美しい景に一瞬で心を奪われた。真っ白な
滝の水が夜になり青さを宿しつつ凍ててゆく。「月に青さを貰ひつつ」の
措辞にしびれた。 華凜
紙を漉く吉野の水は痛かりし
今井勝子
句評 一読、国栖の里へ紙漉きを見に行った日の記憶が甦った。吉野は
清らかな水の里。その寒の水を使った紙漉きは清らかであるが故に冷たく
手に痛い。「痛かりし」に全てを記し見事。 華凜
読初は待ちに待つたり諷詠誌
立花綾子
グランドに残る足あと日脚伸ぶ
足達晃子
これよりの余生いとほし冬すみれ
森本昭代
三枚の肩たたき券お年玉
古宮喜美
武蔵野に富士あらはるる初景色
ざわざわも清しき音よ初詣
七種は身近なものの三鷹産
お神酒うけ火の勢ひ立つどんどかな
一瞬に神の加護ありどんどの火
火の色に徳といふものとんどの火
灯すごと社の門の寒つばき

跳びはねる金ンの兎絵初便り
書初や小さき児の手を支へつつ
母が書き龍の一文字凧揚げる
御神渡り期待の湖岸氷り初む
残雪の甲斐仙丈の夕茜
春兆す男の子の腕のブレスレット
梅香る南信州我が生地
風花の美し海の街なればなほ
早梅に夜明けの前といふ香
深海の音を潜めて竜の玉
雪降りてうそのまこととなりにけり
初天神お師匠さんと会いにけり
寒紅をさす別れ告ぐその前に
束ねても香一本水仙花
息継ぎもできぬ恋文懸想文
路地に遊ぶや京風の寒すずめ

寒柝の一打に星の瞬きぬ
足達晃子
句評 寒柝の音を通じて、冬の澄みきった夜空や冷たい空気感まで
伝わってくるよう。この句を見た瞬間、昔行った白川郷の星空を思い
出した。季題から季節全体へと広がる秀句。 華凜
顔見世にゆかねば京の人ならず
黒田泰子
句評 「京の人」に注目。最近京都に引っ越してきた人という訳ではなく、
百年、いや応仁の乱以前から続く家系を「京の人」というと聞いたことがある。
「顔見世」にゆかねば。 華凜
天心へ寒月固く上りけり
信貴 宏
来る人のなき元日の薄化粧
浅野宏子
色変へぬ松色変へぬ紀伊の石
中谷まもる
ペダル踏む顔に北風貼りつけて
宮下美和子
花菜風子ども歌舞伎の紙垂揺らす
夕東風の一つ灯りし舟屋かな
さし網に白波立てる鰆東風
練りあげし奈良墨匂ふ涅槃西風
伊根なれや春風弾む舟屋口

春風や島影とほく瀬戸の凪
牛窓の丘より瀬戸の四方の春
牛窓や春まだ浅き港町
ぢいの背ナひ孫の背ナを春の風
春風やこころまあるく四世代
純白のシテの装束冬の宮
さみしさは文には書かず冬ごもり
埋火や小面何か言ひた気に
南座は近くて遠し都鳥
蕪村忌の京島原にちらと雪
着流してこその文士の褞袍かな
三味の音も小唄も松原屏風より
玉三郎醜女も演ず古暦
喪に服すことも忘れて河豚食ぶる

もみぢ散ることさへ涙もろくゐる
吉田るり
句評 俳句には感性が大切。作者の純粋で美しい感性には常より感心
している。この句を見た瞬間、作者の心が筆者に深く伝わり共鳴した。
選後に作者のご主人様が年末にお亡くなりになったと。心よりご冥福を
お祈り致します。 華凜
路地一つ違へて迷ふ近松忌
久保田まり子
句評 「近松忌」という季題をよく捉えている。近松の心中物をふと思い
出す。生きる事を道とし、その路地を一つ違えてしまうこともあると。
暗喩の見事な句。 華凜
過ちの二つや三つ木の葉髪
太田公子
先見ゆる暮しに慣れて日向ぼこ
古山丈司
月食の闇を楽しむ初冬かな
井田國敬
噛み合はぬ会話の弾む日向ぼこ
黒津知江子
牧閉ざす日の杣道の風粗し
遠野てふ名にみちのくの秋深む
南部曲屋の馬塞にも柿すだれ
星空に濡るる一夜の秋の宿
わが知らぬ町の一日の秋まつり
南部囃子や相伝の帯締めて
どんどはれにて炉咄も尽きにけり

歴史訪ふ思ひ思ひの冬帽子
古墳へと冬紅葉また冬紅葉
冬ざれのどの石室も傾ぎをり
大綿に風土記の丘といふところ
大綿や史実はいつも哀しかり
太子の里訪ひし大綿日和かな
帰り花ここは太子の眠る里